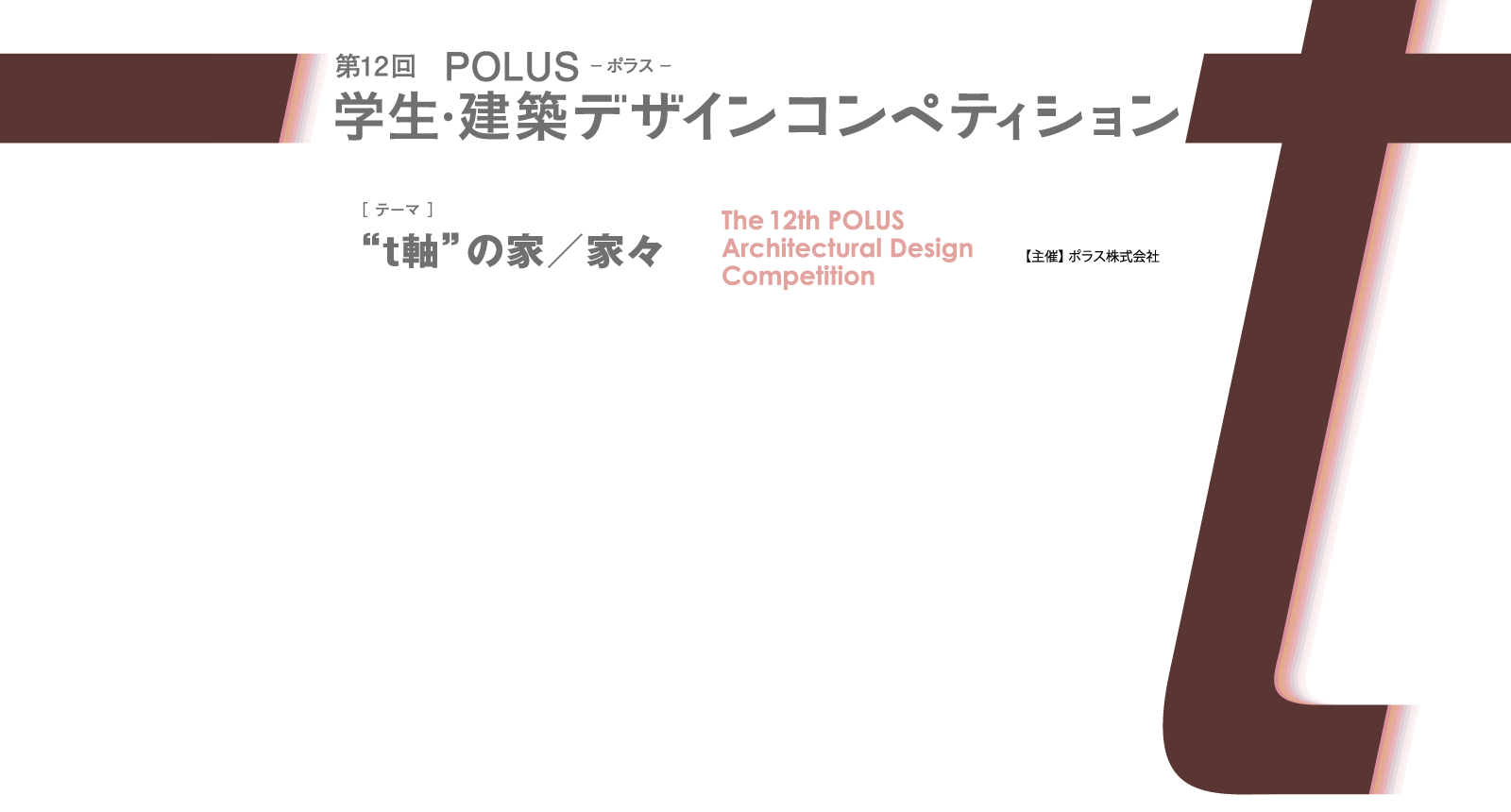
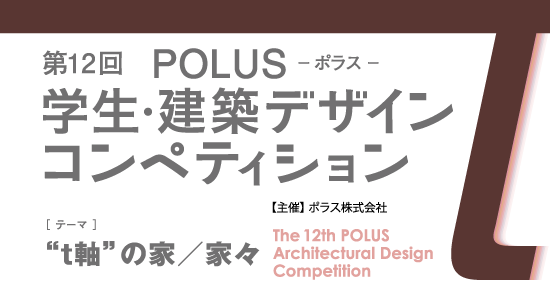
CRITICISM―審査講評
審査委員
今井 公太郎東京大学生産技術研究所 教授

-
今回のテーマは、建築の時間的な変化に注目した王道の課題でした。 登録数は3桁!に迫り、合計で599もの提案が寄せられる非常に高レベルなコンペとなりました。
最優秀案「暮らしは路にこぼれて」は、路地と住宅の関係を反転させ、豊かな路地空間を新たな方法で生み出す提案です。設計の通り芯を決める際に揺らして「崩す」という斬新な手法を用いた点が印象的でした。大まかな幾何学的関係を定めた後、それを基盤に設計を進め、最後まで豊かな空間の構築と調整を積み重ねていたことが評価されました。システムと自由のバランスを的確に活かし、設計プロセス自体も含めて時間の堆積として建築に反映できたことが、勝因につながったと思います。
優秀案「編まれる時間のすまい」は、レベル差を空間体験に積極的に取り込み、日常の移動に内在する時間的なファクターに注目した提案でした。レベル差を持つ複数の住宅が絡み合い、ネットワークを内包した集合体を形成することで、新たな可能性を感じさせてくれました。
入選案もいずれも高い完成度を誇り、たとえば土壁を用い、素材の時間的な変化の差異に着目したユニークな提案など、多様な視点が見られました。
ポラスの学生建築デザインコンペは、参加者が過去の優れた提案を参照できるようになってきたことで、全体のレベルが着実に向上し、提案内容も安定期を迎えつつあります。今後のさらなる展開と進化に期待しています。
原田 真宏芝浦工業大学 教授

-
約1000件のエントリーと約600の応募作品があったとのこと。例年のことではあるけれど本当に多くの建築学生が参加するこのコンペは、ひょっとしたらものすごい能力を持った思考装置なのかもしれないと思っています。これだけの建築系の新しい頭脳が「一つの課題」を思考するのですから、解決が難しい、しかし重要な難題に対して、解答を見つけられるかもしれない。
そんなことを考えて、今回の課題「t軸の家/家々」を出題させてもらいました。 課題文にもあるように、世界の持続可能性を求めるときに、空間の普遍性の追求という20世紀型の理想に加えて、時間を超える普遍性が重要であることは、すでに共有された全地球的な課題です。しかし、時間軸方向に建築を開いてしまうということは建築の完結性が揺らぐことになり「作品性」や、ひいては建築家という「作家性」という概念の存続も危うくなる。そんなジレンマに皆さん向き合われたはずです。
そんな中、受賞された作品のいくつかは、ハードにもソフトにも建築に流動性や循環性を取り込んだものとなっていましたし、建築家像も絶対的なビジョニストというよりも、自走するシステムのマネージャーのように捉えられているものもあったりと、新しい「作品性」や「作家性」にも踏み込んだ提案になっていたように思います。
もちろん、それらが新しい「正しさ」と確定されたわけではありません。しかし考え続ける運動が生まれ、考えるべき対象として共有されたことには確かな価値があります。 単なるアイディアコンペを超えて、社会課題について思考する、ある種の輪郭のないシンクタンクとしてこのコンペが継続していったら、、と審査員としてというより一建築家として願っています。来年以降にも期待したいと思います。
中川 エリカ中川エリカ建築設計事務所

-
今年も多くの応募をいただき、1次審査・2次審査とも白熱した議論が交わされた。応募者・関係者の皆さんにこの場を借りてお礼を申し上げたい。
「暮らしは路にこぼれて」は、内外ともひとつとして同じ場の質がなく、居場所の選択肢も数えられないという、量とは違う魅力がある。設計プロセスにおいて、コントロールできないスタートから生み出された過程を途中からは作家の思想・こうあるべきだという強い意思で変形していくダイナミズムがあり、それこそがとても創造的だと感じた。このプロセスが示すのは、現代建築の創造的な問題そのものであり、自分の問題とも重なり、とても共感した。
「編まれる時間の住まい」は、t軸の家というテーマだからこそ出てきた提案で、連続する時間体験をそのままかたちにする面白さがあった。外部空間が立体的で魅力があるのだが、内部と断絶してしまっている印象があり残念だった。1階から上がる階段と段差を持つ内部空間とが切れ目ない体験になっていたり、内部にいても外部の立体性を感じられたり、家の中でも集まって住む豊かさを感じられるような工夫があると、より素晴らしい提案になったのではないか。
「レジリエントな土壁」は、マテリアルの持つ固有の時間をt軸というテーマに結びつけた提案で、単体の家の模型はとてもユニークで魅力があった。家が集まった時に、そのユニークさが家の数以上に増えることを期待したい。
野村 壮一郎戸建分譲設計本部 設計一部 部長

-
今年度はt軸という「時間性」がテーマとして掲げられました。それに対し個人的には「時間軸の変化を外形的に捉えた提案」と、「減築や増築、住み替え等のプログラムの提案」とに多くの応募作が大別され、例年よりはコンセプトの傾向が固まっていたような印象を持ちました。その分いつもよりは一次の段階で優劣がはっきりと現れたかもしれません。しかし二次審査に進むと模型やプレゼンによって事前の印象は大きく変わり、やはり公開審査の重要性を再認識させられました。
そして最優秀に輝いた【暮らしは路にこぼれて】は、一見フリーハンドに思える有機的な形状の7邸の住宅群で、様々な世帯や世代、また現在の世相を反映した多様な構成の家族が「同じ土地に住む」提案でした。その複雑な形状の住宅群の面白さに目が行きがちですが、実は対象地をいっぱいに使って建物の隙間の敷地部分をどう暮らしに寄与させるのかを綿密に考え、各世帯を巧みに配置したランドスケープの提案であることが分かりました。その必然的な共有のカタチである点と、誰も置いていかない優しい建築であることに大変感銘を受け、実事業においても忘れてはならない視点であると考えさせられました。他の候補作も含め、素晴らしい提案をありがとうございました。
また昨年から実物件化や3年生以下にスポットを当てるRI賞とUJ賞が設定されています。高名な建築家の方々の声を聞ける貴重な機会です。次回も多くの学生の皆様に意欲的に応募して頂ければと思います。
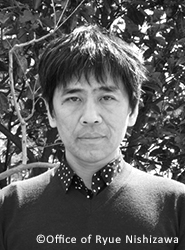


今年はたいへん多くの応募があり、審査会も活気に満ちたものとなった。600近い応募作品の激戦の中、見事最優秀となった小林・野澤案「暮らしは路にこぼれて」は、満場一致で選ばれた。偶然性を取り込む実験的な設計プロセスを経ながら、同時並行で建築家の意思が介入し、通りや街並みの豊かさを作り出すというもので、多様性をどう作り出すか?という設計上の大問題に見事に応えていると感じられた。入選の儲・宋案は、土造、鉄骨造、木造の三種類の工法で全体を作り出すというもので、異なるリズムの時間軸が重なり合う住宅地を作り出した。T軸という課題に対してもっとも王道的な解答だった。優秀賞となった所・井口・鈴木案は、上下に起伏する住居が重なり合い呼応するという案で、構成の面白さもさることながら、部屋構成のプランニングを無時間と考えて、壁で仕切られない場の連続を有時間と捉えるという視点が面白く、T軸を平面計画に置き換えるその抽象化の仕方が独創的と感じた。村上・中村案はたいへん高密度な立体住居で、全体で大きなひとつの大家族という雰囲気の面白さがあった。もっと面白くなる案だと思う。矢野・菊池・山之口案は、彫刻的と言える造形性に富んだ作品で、形の力強さが評価され、またその素朴なロマンも好評だったが、住居についての提案がなかったのが残念だ。