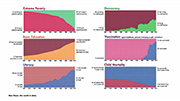The World Around – Architecture’s Now, Near & Next レポート
文・写真(明記以外):柴田直美
プレゼンテーションデータはDezeenより
(https://www.dezeen.com/2020/01/25/the-world-around-conference-new-york/)
「The World Around – Architecture’s Now, Near & Next」というカンファレンスが2020年1月25日にニューヨークで開催された。会場はニューヨークタイムス本社ビル(設計:レンゾ・ピアノ)内のTheTimesCenter auditorium。10:30から始まり、昼休みを挟んで、18:30までという1日がかりのイベントには、世界中から建築家やデザイナー、キュレーター、アーティストなどが集まり、15〜20分程度のプレゼンテーションやパネル・ディスカッションを行なった。
会場では、Head Hi Book Kioskというポップアップの書籍販売コーナーや、家具メーカーのArperが自社のプロダクトでThe Arper Loungeという休憩ラウンジをしつらえたほか、Parlor CoffeeのコーヒーやVan Leeuwen Ice Creamのアイスクリームを振る舞う時間帯もあり、PIN-UP Magazine の特別号が配布された。
主催したThe World Aroundは2019年にベアトリス・ガリリー(Beatrice Galilee)、ディエゴ・マロキン(Diego Marroquin)、アレグサンドラ・ホドコウスキ(Alexandra Hodkowski)の3氏によって設立された、建築的言論を深めるプラットフォームで、今回のカンファレンスを始めとして、世界的なネットワークをつくることを目指している。事前予約で満席となったことから期待の高さが伺える。
エクゼクティブ・ディレクターを務めるガリリー氏は昨年までThe Metでダニエル・ブロドスキー・アソシエイト・キュレーターとして建築デザインに関わる近代現代コレクションを始め、A Year of Architecture in a Dayというカンファレンスを立ち上げた実績がある。
https://www.metmuseum.org/events/programs/met-speaks/symposia/a-year-of-architecture-in-a-day-2019
その経験から、「建築家やデザイナーの智見をシェアすることで、楽観的に見ることが難しい、私たちを取り巻く今の世界を理解して、世界を変えることができる」とガリリー氏が冒頭に述べたように、Reconnecting with the world around(つなぎ直す)というセッションで始まり、Reconstructing with the world around(再構築する)というセッションで終わる構成であった。
セッション:Reconnecting with the world around
ニューヨーク近代美術館R&D部門のディレクター兼建築・デザイン部門のシニア・キュレーターであるパオラ・アントネッリ氏(Paola Antonelli)が昨年、ミラノのトリエンナーレ美術館でキュレーションしたBroken Natureという展覧会について、「エコソフィ」(ecosophy=フランスの哲学者で精神分析家のフェリックス・ガタリと、ノルウェーの哲学者のアルネ・ネスによって1973年に作られた、ecologyとphilosophyの造語で、エコロジカルな調和や均衡の哲学)をキーワードに、他の種と同じように人類もいつか滅ぶが、「どうやって」滅ぶべきか、次の種に何を残すか、ということを考えたと説明した。展覧会が開かれたミラノはミラノサローネが毎年開催されることから、市民のデザインへの意識も高い。市民に今のどういった行動が、ずっと先の地球環境をどのように変えるのか、ということを伝えるための展示だったとアントネッリ氏は振り返る。
中国の建築事務所、DnA Design and Architectureを率いる徐甜甜氏(Xu Tiantian)は『Rural Regeneration in Sonyang(松陽県の地方再生)』というタイトルで、浙江省麗水市松陽県での地域再生プロジェクトについて、自身が手がけた建築を中心にプレゼンテーションをした。松陽県は最後に残された中国本来のエリアとも呼ばれているが、若い世代は街へ出てしまうという問題を抱えていた。松陽県の南に位置する逐昌村につくったHakka Indenture Museum(石倉契約博物館)は、この地に住む客家人(中国南部を原郷とする漢民族のひとつ)の歴史的遺産と受け継がれてきた文化をそのまま体験するような場所として設計されている。村人の誇りで明朝の高名な宮廷学者であった王京の出身地であった歴史を誇っている王村にある王京の記念碑を中心に計画されているWang ding Memorial Hall(王景記念堂)、洪水でふたつに分けられてしまった街をつなぐShimen Bridge (石門廊橋)は橋の上で市場やパレードができる歩行者のための橋、かつて黒糖の名産地として知られた興村のBrown Sugar Factory(紅糖工場)は、伝統的な砂糖製造過程をライブパフォーマンスとして見せることで、砂糖の値段の維持にも貢献し、茶畑などに転向していた農家がサトウキビ栽培に戻ることにも繋がっている。これらの建物の建設を通して、失われつつあった技術を再興したり、地域にある文化遺産を価値にして、雇用機会を生み出すことで、持続可能な地域再生を目指している。「Architectural acupuncture(建築的鍼治療)」というキーワードが使われていたが、この言葉は以降のプレゼンテーションで度々耳にした。
ニューヨークを拠点にするアーティスト、マイケル・ワン氏(Micheal Wang)は、かつてニューヨークに生育していた46種の種を展示したガバナーズ島での展示「Extinct in New York」について話した。朝の霧程度の湿度が必要な種すら消えていっている現状、人間の手が入らなければ存続できない種があるということを伝えた展覧会であった。
ジョシュ・ベクリー氏(Josh Begley)は200,000枚のgoogle earthの画像で米国とメキシコの国境2000マイル(約3200km)をひたすらなぞる映像作品『Best of Luck with the Wall』の上映。トランプ大統領による「国境の壁」計画で注目されたメキシコと米国の国境は、一部はフェンスがあるなどするが、ほとんどは国がつくった概念の境界線であり、その地理から何を感じるのか、を問う作品。
https://fieldofvision.org/best-of-luck-with-the-wall
デイビッド・オライリー氏(David O'Reilly)は『Everything』という、どこにでも行けて、動植物や人工物、素粒子、宇宙など、何にでもなれて、何をしてもいいというシュミレーション・ゲームのプレゼンテーション。競争するゲームではないし、AIに任せてオートプレイさせることも可能。「人間と環境は一心同体で影響しあっていることを忘れてはいけない。聞こえている声や写真に写った自分に違和感を感じることもあるように、自分たちの知覚の限界を知ることも重要。」とオライリー氏は語る。
https://youtu.be/HdJk8ROpuEo
イブラハム・マハマ氏(Ibraham Mahama)は、都市のモキュメンタルな建物をジュートの袋で覆う作品シリーズでヴェネツィア・ビエンナーレ、ドクメンタ14、ミラノサローネで発表しているアーティスト。アジアでつくられたジュートの袋が、ガーナから西欧へコーヒー豆などを輸送する際に使われている。その世界的な貿易の過程で、労働者が刻印した日付や名前が刻まれている袋は、ガーナを始めとしたアフリカ諸国がコモディティ貿易に依存していることの象徴である。2015年にはSCCAという廃墟だった工場を転用した現代美術のオルタナティブスペースをガーナにつくっている。地理的・経済的に貧困層が多い地域の子どもたちに、違う世界の見方を伝えることが重要と語る。
ジュリア・ワトソン氏(Julia Watson)は現在、準備中の新著『Lo—TEK, Design by Radical Indigenism』について話した。子どもの頃にテレビで1989年のエクソンバルディーズ号原油流出事故を見たことで、海洋生物学者になりたいと思った彼女は、現在は生態系の専門家である。世界各地に残る焼畑の文化や、アマゾンのカヤッポ族がもつ自然と人間は一体であるという世界観、インドネシアの魚と米を同時に育てる水田養魚など、単一機能の構造でなく、文化と生態系を体現するような技術によって、自然と共生する方法についての著作となる予定。
石上純也氏は、ガリリー氏が「table」を見たときから注目しており、ついに招聘できたと期待を寄せられていた。敷地に生えていた木々を全て、新しい敷地に移した「アート・ビオトープ那須 水庭」については、全部の植物を計測したおかげでランドスケーププロジェクトにも関わらず、それらの間を設計することができたと語る。植物の移動は数年かけて行うのが通常だが、それでは周辺の生態系が壊れてしまうことを懸念して、数時間で動かせる機械(ブルドーザー)を導入したという。全部の池が繋がっていて川へ流れるという田と同じシステムはかつてそこに田園があったことを想起させる。「New abstraction of Another nature(もう1つの自然の新しい抽象化)」という哲学に基づき、元からあったものだけを使って、新しい自然を生み出しており、「何が新しいもので何が元からあったものか曖昧になっているが、自然と人工の間の自然のような、自然には起こりえないことが実現できた」と石上氏。
セッション:Design Focus
ここで一旦、昼休憩となり、午後はDesign Focusというブルース・マウ氏(Bruce Mau)のプレゼンテーションから始まった。マウ氏は、カナダのトロントを拠点とするデザイナーであり、レム・コールハースの著書『S, M, L, XL』のアートディレクションを手がけたことで知られるが、近年はより良い未来のために社会的運動をどのようにデザインするかという取り組みをグアテマラやデンマークで展開している。過去100年以上、デザインを解決のために使ってきたが、現代は「Redesign everything」という意味で最もおもしろい時代にいるとマウ氏は語る。フィラデルフィア美術館での「Work on What You Love(好きなことをしよう)」展で掲げられていた24 Principles of Design(デザインの24の原理)についてプレゼンテーションをした。Fact based optimism(事実に基づいた楽観主義)がデザイナーには必要であるとマウ氏はいう。どの時代よりも恵まれているこの時代に感謝するべきであり、生死を分けるような問題も減っている。環境の変化は喜ぶべきことではないが、そこに対して何かすべきことがあるというのが事実であり、「We must be critical, not cynical(批評的であるべきだが、シニカルであるべきではない。)」という。世界を反転して見てみることも24の原理の1つ。「Good is bad, Bad is good. Terrible is awesome!(良いことは悪いこと、悪いことは良いこと、ひどいことは最高!)」と、デザインという態度を拡張し、活動を続けるマウ氏のプレゼンテーションは非常にわかりやすいものであった。2020年夏に『MC24: Bruce Mau's 24 Principles for Designing Massive Change in your Life and Work』が出版予定。
セッション:Translating Identity: Design in the Age of Big Data
リアム・ヤング氏(Liam Young)の『Choreographic Camouflage』という映像作品が上映された。ヤング氏はBBCに「the man designing our futures(未来をデザインする男)」と紹介されたことがある建築家。映像は全編、自動運転の車で使用されているスキャン技術を使用して撮影されている。
続いて壇上では、ヘリット・リートフェルト・アカデミー建築学部長であるニック・アクセル氏(Nick Axel)がモデレーターとなり、登壇者がまずプレゼンテーションをし、その後、パネル・ディスカッションへと進んだ。
まずアクセル氏がテクノロジーとの関係を考えるキーとなる例を紹介した。ロバート・ラウシェンバーグ(Robert Rauschenberg)の《Mud Muse》、クー・ジュンガ(Koo Jeong A)の《Density》、1940年代にピッツバーグ郊外に建てられた公営集合住宅、1970年代の美術館と一緒の建物に入っているスウェーデン政府(国会)、中国の社会信用システム(social credit system=社会的な信用度をスコアとして数値化するシステム。スコア次第で、金融・福祉などのサービスの優待、または公共交通の利用が制限されるなど)のアプリなどを挙げた。
キャロライン・クリアド・ペレス氏(Caroline Criado Perez)は、『Invisible Women』の著者。男性が集めたデータをもとに作られた社会のサービスやプロダクトが女性に合わないが、逆に男性が赤ちゃんをスリングに入れてみたら短過ぎて、それは女性中心(female centric design)のデザインだったことがわかった。心臓発作の画像検索をすると男性ばかり、クッキーの画像検索には女性がいることが多いなど、画像のデータセット(Image dataset)はバイアスである、とも指摘する。「女性を男性のように扱うことが平等さではない(Equality doesn’t mean treating women like men)」、「性別ごとのデータを収集する(Collect the sex disaggregated data)」、「仕事において最高のチームになりえる(The best team for the job)」ことが大事だと結論づけた。
2020年1月までMOCA Trontoで展示されていた『Age of you』をキュレーションしたシューモン・バサール氏(Shumon Basar)は「Age of you is the new Age of Extremes(私たちの時代は新しい『極端な時代』(歴史学者エリック・ホブズボームが著した20世紀を包括的に捉えた本)である)」という。マーシャル・マクルーハンは1990年に亡くなったので、デジタル時代の到来を見なかったが、現在のデータ中心の世界を予言していた。デジタル時代の到来とともにスクロール、スワイプなど新しい言葉が生まれている。
次にプレゼンテーションをしたエヴァ・フランク氏(Eva Franch)は、AAスクールのディレクターであり、「Architecture in translation」と題して、データとアイデンティティについてプレゼンテーションをした。この10〜20年の間に、アカデミック界を英語が主導するようになってきたが、AAスクールでは81の違う国籍を持つ教師や学生が集まっており、いろいろな言語や文化をバックグラウンドに持っていることによる多様性を理解するようなプロジェクトを進めている。「もっと自分が何者であるか、他者が持つ自分が知り得ないことはなにかを知ることが必要だ」と締めた。
セッション:In Conversation
休憩の後は、ガリリー氏がモデレーターを務め、エリザベス・ディラー氏(Elizabeth Diller)とキャサリン・インス氏(Catherine Ince)の対談で始まった。インス氏は、ディラー・スコフィディオ+レンフロが設計をしているV&A EAST(2023年竣工予定)のチーフキュレーターである。
V&A EASTは、ロンドンの東側、クイーン・エリザベス・オリンピック・パークに建設中でオリンピック時に報道局だった建物を転用しており、Here Eastの文字が入った屋根が特徴的である。リサーチ・センターにはフランク・ロイド・ライトがカウフマンのために設計したオフィスも含めた膨大な作品や資料がコレクションされており、保存修復、ワークショップなどの機能が入った複合施設。ディラー氏は「『collecting』、収集のロジックに興味があった。」という。ベンヤミン(Walter Benjamin)の「I am unpacking my library. Yes I am. The books are not yet on the shelves, not yet touched by the mild boredom of order.」という一文のこの方法がとっても好きで、本を箱から取り出して、本棚のどこに置こうかと考えているのはとても美しい瞬間であると思うというディラー氏。ブロードキャスティングのために作られていた建物には窓がなく、人の活動のためにつくられていなかったので、建物の中心を掘削(excavated)して、パブリックスペースとした。その中心からいろいろなところにアクセスできるようになっていて、その中心から、ファッション、テキスタイル、演劇、陶芸、デザイン、建築などのとにかくたくさんあるコレクションを見ることができるように設計している。アクセスしにくい位置にあるコレクション品はロボットを通路の奥に走らせて鑑賞するといった技術で補完するなどを考えている。
対談ではインス氏がV&A EASTは「live place to workのプラットフォームとして設計されている。」と説明し、ディラー氏は「修復士の『暗いところがいい。』というリクエストを受けて、キュリトリアルとコンサベーションとデザインの関わり方を考えるのはとてもおもしろかった。」と振り返った。
セッション:Reconstructing with the world around
アーバンデザイナーであるエマニュエル・プラット氏(Emmanuel Pratt)はシカゴの南エリアの街、サンボーン(Sanborn)での活動「Sweet Water Foundation」を紹介した。「Sweet Water Foundation」は第3セクターであり、健康的で安全なコミュニティスペースを提供することで、近隣エリアの再生を目指している。サンボーンの一区画が1936年の開発の時点で、人種による住居の分離が決定づけられた歴史から現在までの変遷を探り、この土地の価値を再考した。そのうちのひとつの活動は、誰でも入れる庭を作ったことで、子どもが学校の屋外学習に来たり、高齢者が野菜を作ったり、ファーマーズマーケットや料理クラス、Tシャツプリントワークショップ、木工ワークショップなどが開かれることにつながった。人々が場所を作り、南シカゴのネガティブなイメージを変えることに成功した。
チリの建築家、セシリア・プガ氏(Cecilia Puga)は「Time Fades」と題して、Palacio Pareicaの修復プロジェクトについて話した。Palacio Pareicaは近代化の途中であった19世紀後半に建てられた植民地時代の建物であり、所有者の家族が亡くなった後は転売され、1985年の地震により大きなダメージを受けて、悲惨な状態だった。2011年に国が買い戻し、2014年にコンペに勝ったプガ氏らが修復にあたり、2019年に完了したプロジェクト。
建築やアートなどを手掛けるサムシング&サン(Something & Son)は「The Manuals」と題して、FARM Shopという都市での農業の可能性を探求したプロジェクトやBarking Bathhouse Cultural Olympiaという期間限定のスパで癒しを提供するプロジェクトなどを紹介した。彼らの著書「The Manuals」では、人工物をどうやって利用してエコシステムにするかということを紹介されている。
スイスの建築家、バラッチィ・ヴェイガ氏(Barozzi Veiga)は彼らのプロジェクトのひとつ、Tanzhaus Zürichという劇場について話した。「建物に適した特徴を与えることが大事である。モニュメンタルとそうでないものの間を探している。」とヴェイガ氏は語る。
バーレーンで建築家/キュレーターとして活動するノウラ・アル・サイェ・ホルトロップ氏(Noura Al Sayeh Holtrop)は、バーレーンの都市、ムハッラク(Muharraq)の再生プロジェクトについて話した。ムハッラクは1930年代に油田が発見されるまで、天然真珠の一大産地として知られていた。2012年に「バーレーン真珠採取の道」や周辺の建造物と関連する漁場がUNESCOの世界遺産リストに登録されたが、往時を偲ぶ建物は荒れ果てていた。気候やオリジナルの建材などを大切にしながら、少しずつ手を入れている。ヴァレリオ・オルジャッティによるビジターセンターやクリスチャン・ケレツによる立体駐車場などを含む、これらのムハラックの再生プロジェクトは2019年のアガカーン賞を受賞している。
https://www.akdn.org/architecture/project/revitalisation-muharraq
重松象平氏が今回の長いイベントのトリであった。「Extending the Museums」と題したレクチャーは、世界中で開かれている芸術祭が196もあるという話から始まった。美術館のコレクションがどんどん増えるいっぽうであるのは自明でMusum Extensionをどう考えるか。2016年に完成したケベック美術館や進行中のバッファローのオルブライト=ノックス美術館の増築、実現しなかったホイットニー美術館の増築などの紹介の後、ニューミュージアムの増築案を紹介した。
グレタ・エルンマン・トゥーンベリさん、Ai、ビッグデータなど、今の話題が出つつ、コモディティ(Commodity)、ミソジニー(misogyny)といった以前から議論されつつも依然として前進しない問題も取り上げている。建築のプロジェクトのほとんどはローカルのコミュニティとどう関わるかという点に注目されていて、ここを抑えると街が再生するというようなポイントを探し出して働きかける、「Architectural acupuncture(建築的鍼治療)」という言葉が印象に残った。一見、デザインの話題から切り離されてしまいそうな分野も包括的に話す、おもしろい機会だと思った。4月22日のアースデイにもオンラインのトークを配信するなど、今後の活動も楽しみである。