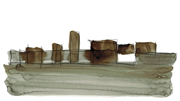RCRアーキテクツ プリツカー賞受賞記念講演会「Shared Creativity」 レポート
28年ぶりに日本でプリツカー建築賞受賞式典
2017年5月22日(月)、東京大学安田講堂において、スペイン北東部のオロットを拠点とする建築設計事務所RCRアーキテクツの代表、ラファエル・アランダ氏、カルメ・ピジェム氏、ラモン・ヴィラルタ氏による講演が開催された。RCRアーキテクツは第39回プリツカー建築賞を受賞し、5月20日(土)に迎賓館赤坂離宮で授賞式典が催されたが、日本で受賞式典が開催されるのは28年ぶり。講演にはグレン・マーカット(2002年受賞)、リチャード・ロジャース(2007年受賞)、SANAAの妹島和世と西沢立衛(2010年受賞)、ワン・シュウ(2012年受賞)の歴代受賞者が列席し、3人が一緒に講演するのは初めて、という記念すべき講演会となった。
Shared Creativity
1990年初来日し、その自然感に打たれたという3人は、「日本は私たちの全てのインスピレーションの源であり、私たちの出発点。」という。それまでは1人、または2人で働いていたが、初来日以降、3人で働くスタイルになった。以降、それぞれの名前をとったRCRアーキテクツという名前で活動をしている。
3人が一番大切にしていることは、「shared creativity」。手は6本、でも声はひとつ。ジャズのセッションのようなもので「フュージョン」してひとつのユニットになっている、と説明する。今回の来日で教えてもらった「阿吽の呼吸」、「3人寄れば文殊の知恵」という言葉も、彼らの共同作業を理解するキーワードという。
RCRアーキテクツの拠点、オロット
鋳造所を改修したRCRアーキテクツのオフィスがあるオロット(人口:およそ3.5万)という町はピレネー山脈が見えるスペインの北部にある。火山地帯で、手つかずの自然ではなく、段々畑など、人間の手が加わった自然。彼らには、そこに「大好きな特別な森」があるそうだ。火山地帯なので、緑が生えるところは多くはないが、そこに残っている小さな家や祈りの場、湖岸の景色が彼らの原風景。ベーシックな素材を使った農家や金属をはりつけた外観を持った家とのコントラスト、玄武岩から生えている緑、岩山の六角形の断面など彼らが暮らすオロットの町そのものが、彼らの建築を理解してもらうために一番重要なものである、と断言する。
日本からのインスピレーション
「京都の寺社仏閣でみた石畳の繊細さ、石庭の神秘さ、そこに宇宙を感じることができました。ディテールに感銘を受けましたし、桜が咲く頃に京都に行ったのは幸運でした。また高野山で、間と間がつながる部屋に滞在し、それを体感したのはセンセーションでした。」とRCRアーキテクツの3人は初来日を振り返る。今回の来日では、日本の木材がどう生えていて、どう建築になるのか見たいと、吉野の山や製材所を訪れた。吉野の学校に訪問し、生徒と木について話した際に、彼らが木板を卒業記念としてもらうなど、地場の木材について自分たちの木であると自覚を促されている、という印象を受けたという。「建築の素材が大事だと思っているので、その起源を知ることが不可欠である。今回は、木材のルーツと void(間)を知りたい」と思っていたそうだ。京都で龍安寺を訪れた際には、建築と景観と石庭とのハーモニーを印象深く体感したという。「いろいろな音色が違う音がする。建築がもつ力。素材の素晴らしさ。このコンセプトを静寂さを通して体感できました。」という彼らが日本の建築に見出したものは、彼らがこの30年間で設計してきた建築を表現する言葉と重なると思った。
Atmosphere
「その場所の特性をどのように活かし、どんなプログラムをつくるのか。そこの雰囲気を考え、建物を使う人がどう感じるか、何かの感情を呼び起こすものであってほしい。そのためにはそこの場所のエッセンスであるルーツが何であるのかを理解することがとても大切であり、それを知っているからこそ応用ができる。すべての建築、景色にはロジックがある。」と彼らは語る。
彼らがいくつか自作を紹介した中で、「その場でしかできない建築をつくった」という言葉が繰り返された。そこにある環境から導く最小限の操作で生みだされる新しい関係性や気がつかなかった感動を与える彼らの建築。その静謐な生命力には、スペインの気候が持つ外部空間の豊かさや快適さを始め、歴史や自然、地形などからの多くの学びが編み込まれている。「これからの30年もこの仕事をしていきたいと思います。」と語る彼らが作り出す建築には人々が集まり、その土地ならではの風景をつくって行くのだろう。建築を学んでいる学生への「建築家というのは情熱をもってとりくんでほしい職業です。人生というより生き方です。」という示唆で講演会は締めくくられた。